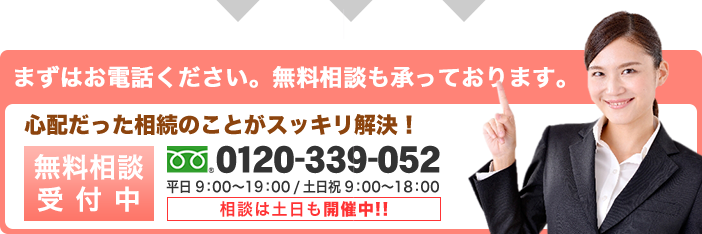遺産相続の無料相談実施中。相続相談ネットは、あなたの遺産相続をサポートします。
遺贈について
包括遺贈
包括遺贈とは、財産を特定して受遺者に与えるのではなく、全相続財産の5割とか全相続財産の4分の1のように、割合で相続財産を譲渡することです。
包括受遺者は相続人ではありませんが、民法上「相続人と同一の権利義務を有す」とされているので、プラスの財産だけではなく、債務も引き継ぐことになります。
債務の方が多い場合は、遺贈の放棄をすることができます。
遺言者が死亡したこと、自分に対して遺贈があったことを知ってから3ヶ月以内に放棄の申述を家庭裁判所に対して申し立てなければなりません。
放って置くと単純承認したものと見なされます。
特定遺贈
特定遺贈の場合、放棄に関する期限は定められていませんので、遺贈を放棄するも承認するも自由です。
ただし、受遺者が長期間にわたり放棄も承認もせずにいると、遺贈義務者であるその他の相続人が不安定な立場となります。
それを防ぐために、相続人やその他の利害関係者は、定めた期間内に遺贈の承認または放棄すべき旨を受遺者に対して催告することができます。
また、負担付遺贈というものもあります。
こちらは、遺贈するに当たり受遺者に一定の義務を課すことを条件に財産を与えるというものです。
例えば、「母親の介護をすることを条件に長男に自宅を相続させる」などです。
その他にも、停止条件付き、解除条件付きの遺贈などもあります。
詳しくはお問合せください。
遺贈の効用
遺贈は、必ず遺言によってなされるため、遺言書の作成が必要です。
特に内縁の妻に財産を遺す場合や法定相続分よりも多く与えたい場合などには、遺言書を作成しておくことで、あなたの意思を反映することが可能です。
遺された妻や子供たち、その他面倒を見てくれた方たちへの心配を少しでも緩和させることができるのではないでしょうか。